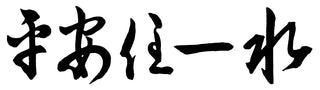京甲冑は実際の甲冑同様にたいへん多くの部位によって構成されています。
したがって、その制作工程も数多く、素材の加工には様々な伝統的技術が駆使されています。
それらのすベてを調和させ、独自の作風を表現するためには、全工程を一貫して加工しうる高い技術が必要とされます。
平安住一水の錺甲冑はその工程の細部に至るまで匠の眼で吟味し、
また、丁寧に手づくりすることによって比類なき伝統美の表現を可能にしております。
ここでは数多くある工程の一部をご紹介させていただきます。

兜鉢の矧ぎ合わせ(かぶとはちのはぎあわせ)
金槌で成形した鉢板を一枚づつ釘でつなぎ合わせます。 独特の形状を作るために、鉢板は大きさと打ち出しを変えたもので組み上げていきます。

鍛金(たんきん)
平らな鉄板より切り出し、 金槌で様々な形状に成形します。 写真は面頬を打ち出しているところです。

小札生地(こざねきじ)
精密に切り出した板を波形に成形し、裏打ちします。
写真は錣を制作しているところです。
完成時の形状に合わせ、永年培った勘と技で微調整を行っています。

錺金具生地(かざりかなぐきじ)制作
甲冑を装飾する様々な金具を加工します。
写真は手挽きで切り出した鍬形を、左右対に削り合わせて面を取り、その後 朴炭で独特の光沢をもたせる下地を研ぎだしています。

覆輪(ふくりん)巻き
本金鍍金を施した覆輪を木槌で締めながら巻いていきます。 写真は 脛当の周囲に覆輪を巻いているところです。

面頬(めんぽお)の髭の植え付け
面頬の生地に鉄錆色をつけ、上質の馬毛を髭として植えていきます。

塗箔(ぬりはく)
形状を調整した小札の生地を塗り固め、 本金箔を押していきます。
黒小札の場合は金箔の替わりに漆などを何度も塗り重ね深みのある光沢に仕上げます。

革所(かわどころ)の裁断
匠の眼で厳選された鹿革に伝統的な柄を置いて造った画革を各部の形状に合わせて切り出します。

縅し(おどし)加工
小札の縅し穴を縅し糸で綴じていきます。
甲冑の形状や美しさが決定される非常に重要な工程であり、熟達の技が生かされます。

錺金具(かざりかなぐ)の取り付け
本金鍍金を施した錺金具を各部に取り付けます。
金具は生地の段階で各々の形に加工されていますので、定位置に取り付ける必要があります。

裂地(きれじ)の裁断
籠手、佩楯、脛当などを飾る家地には西陣織金襴を使用。重厚な雰囲気のなかにも、華やかさを醸します。

革所の取付
裁断された画革を縅上げた小札に取り付けていきます。
写真は胴に弦走皮を取り付けているところです。

兜や胴部の組み上げ
入念に加工された各々の部分はここで集められ、組み合わされて完成に近づきます。

仕上げ
完成した甲冑の細部に至るまで、すべての部分が調和するよう仕上げは念入りに行います。
甲冑生地、塗、金箔押し、縅し、さらに仕上げ……
その一工程ごとに細かな手作業で入念に加工され、重厚かつ華麗な作品として結晶していきます。
手作りの錺甲冑を構成する各々の部分はそのひとつひとつがすばらしい工芸品です。
精緻な加工を施したそれらすべてが調和するときにそれぞれのもつ美しさが最大限に生かされるのです。